特集
飲食店・スナック開業でカラオケを導入する際の注意点と費用相場
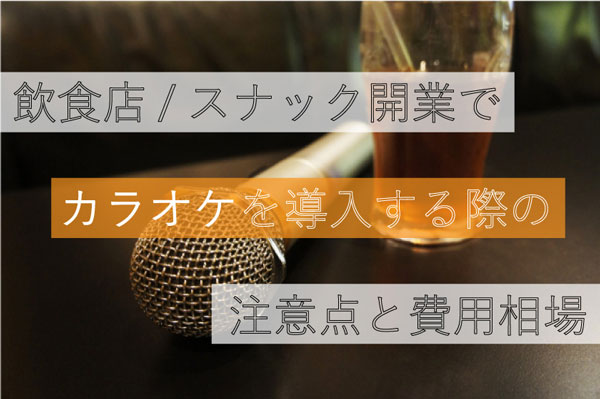
- 目次
居酒屋やスナックなどの業態で飲食店開業を目指す方の中には、カラオケの導入を検討している方もいるかと思います。
しかし、飲食店でカラオケを導入する場合には、機材を揃えるだけでなく、法律や物件の契約ルールに注意を払わなければいけません。
開業後に思わぬトラブルに発展するなどの最悪の状況を回避するためにも、法律の注意点や機材導入にかかる費用について詳しく解説していきます。
飲食店にカラオケを導入するメリット/デメリット
メリット
【1】客単価アップ
本来の目的としていたお酒や会話を楽しむ時間に加えて、歌を楽しむ時間が発生することで、顧客の滞在時間は長くなります。
カラオケの楽しさと滞在時間の長期化により、お酒やつまみの注文が進むという売上アップのサイクルへとつながりやすいのがメリットの一つです。
【2】宴会利用と団体客の獲得
カラオケ付きの飲食店は、年々減少傾向。
しかし、カラオケ需要が落ちている訳ではありません。
友人同士の飲み会やビジネスマンの宴会など団体客が2次会にカラオケ店を利用するという流れは健在。歌って飲める飲食店は希少となっている現代だからこそ、お店を探して来店してくれることが期待できます。
【3】顧客満足度のアップ
一概には言えませんが、会話のみで過ごすお酒の場と比べて、カラオケを利用しながらお酒を飲む場合には、より場が盛り上がりやすいのではないでしょうか。
会話のネタが尽きた時に歌ったり、曲自体が会話のネタになったり、ということもあると思います。
場が盛り上がれば「楽しかった」という記憶を残すことができますし、顧客の満足度にもつながります。その満足度をもとに、リピートへつなげることができるのです。
デメリット
【1】コストの増加
カラオケを導入するにあたっては、機材を導入する費用のほかに、楽曲配信料や著作権料などのランニングコストがかかります。
また、防音環境が整っていない物件がほとんどになりますので、内装工事の際には防音設備のほか防音対策を行なう必要があり、コストが大幅に膨らむ可能性が高くなります。費用相場については、後ほど詳しく説明します。
【2】申請手続きの手間がかかる
カラオケの導入を考える方の多くが、酒類の提供を想定した飲食店かと思います。
深夜0時から午前6時までの間に酒類を提供して営業を行う場合には「深夜酒類提供飲食店営業」の許可申請が必要となり、接待を伴う場合には「風俗営業」の許可申請が必要となります。
いずれも所轄の警察署へ届出をする流れとなりますが、その届出にあたっては、営業方法を記載した書類や営業所の平面図、住民票などいくつか書類を取り揃える必要がありますのでその分の手間はどうしてもかかってしまいます。
【3】近隣トラブルを引き起こしやすい
カラオケを導入する店舗では、音が漏れたり酔っぱらった顧客が騒いだりと、騒音の関係で近隣トラブルが起こりやすいのもまた事実。
近隣との関係性が悪化して営業に影響するのはもちろん、店舗の上階に大家さんが住んでいる場合には契約更新ができなくなるといった最悪のケースにもなり得るので、徹底した防音対策と細心の注意を払うことが重要となります。
飲食店にカラオケを導入する際の注意点
カラオケを導入する前に気を付けておかなければならないのが、「風営法」と「騒音」に関してです。どのようなポイントを押さえておくべきなのか、ここからはそれぞれの注意点について詳しく説明していきます。
接待行為

スナックを経営する場合、その多くは「深夜酒類提供飲食店営業」の届出を行い営業しています。
深夜酒類提供飲食店では、接待行為が禁止となっています。
ただし、ここで注意したいのが、どういった接客が”接待行為”にあたるのかということ。
接待とみなされる行為
接待ではない行為
線引きが曖昧なだけに判断が難しくありますが、カウンター越しの接客でも風営法で言うところの”接待”とみなされ、摘発されるケースもあるので注意しておきましょう。
接待行為をするには、「風俗営業許可」の申請が必要となりますが、その場合深夜0時以降の営業ができません。
なお、「深夜酒類提供飲食店営業」と「風俗営業許可」の二重申請はできないので、どちらの申請をするかはご自身の営業スタイルに合わせて選択する必要があります。どちらにせよ、申請を行う場合には所轄の警察署への届出が必要となります。
遊興行為

「遊興行為」とは、営業者の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為のことを指します。
具体的には、以下のケースが挙げられます。
飲食店においてはダーツバーやスポーツバー、カラオケを導入する飲食店などが挙げられ、場合によっては「特定遊興飲食店」に該当して営業許可を申請する必要が出てきます。
特定遊興飲食店の条件
【1】深夜営業(深夜0時から午前6時までの間に営業)する
【2】顧客に遊興をさせる
【3】顧客に酒類を提供して飲食させる
上記3つすべての条件を満たす場合には、「特定遊興飲食店」とみなされます。
逆に言えば、上記のうち1つでも該当しなければ、営業許可の申請は不要ということです。
なお、特定遊興飲食店の営業は原則24時間可能ですが、東京都では条例により午前5時から6時の間、営業禁止とされています。各自治体によっても異なるので、事前に確認しておきましょう。
騒音・振動・近隣トラブル
カラオケを設置する場合には、前述の通り、騒音・振動への厳重な注意が必要となります。
騒音や振動については、風営法や各自治体の条例で規制基準の数値が定められているのでしっかりと確認しておきましょう。基準を守っていても、近隣トラブルに発展する可能性は大いに考えられますので、防音対策を行なうことはもちろん、開店前の挨拶や開店後の交流を含め、日頃から良好な関係を築いておくことが大切です。
なお、カラオケの導入は対策の有無に関わらず利用禁止とされている物件もありますので、物件取得前に不動産会社や大家さんにしっかりと確認しておきましょう。
飲食店にカラオケを導入する方法
風営法の許可申請は、書類が多くチェック項目も細かいのでとても大変な作業です。しかし、接待行為がある飲食店営業をする場合は外せない工程なので、大まかな流れをここで確認しておきましょう。あわせて、簡単にできる騒音対策もご紹介します。
「風俗営業許可」を申請する

飲食店で接待行為がある場合に必要となるのが、「風俗営業許可」。こちらは、営業所の所在地を管轄している警察署に申請を行います。
申請書類は基本的には全国共通ですが、警察署により追加書類が必要な場合があります。また、個人なのか法人なのかによっても多少異なりますので事前に確認しておきましょう。
必要書類
【共通書類】
・許可申請書
・営業方法を記載した書類
・店舗の賃貸借契約書・使用承諾書
・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
【申請者:個人の場合】
・住民票の写し(本籍記載/外国人の場合、国籍記載)
・法第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・市区町村の発行する身分証明書
【申請者:法人の場合】
・定款及び登記事項証明書
・役員に係る住民票の写し(本籍記載/外国人の場合、国籍記載)
・法第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・役員に係る市区町村の発行する身分証明書
【選任する管理者に係る書類】
・誠実に業務を行うことを誓約する書面
・市区町村の発行する身分証明書
・法第24条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
・管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影/無背景/縦3.0cm×横2.4cm/裏面に氏名及び撮影年月日を記入)
そのほか、申請手数料24,000円がかかります。(証紙にて納付)
万が一、記入ミスがあった場合は訂正ができますので、実印も持参することをおすすめします。
手続きの流れ
【1】上記の書類が揃ったら所轄の警察署へ届出をします。
【2】申請後1ヶ月程度で警察署からの現地調査があります。(※申請者立ち合いのもと実施)
調査としては、照明・音響・床面積等の測定などが行われます。建物の構造や、階数によっては消防署の検査が入るので、非常灯や出入口、非常階段の周辺に物を置かないよう整理しておきましょう。
【3】約1か月半後、警察署の生活安全課より電話で営業許可通知があります。
許可申請を検討している方はこの所要期間も頭に入れて、開業準備を進めなければなりません。なお、この通知をもって当日から営業を開始することが出来ます。許可が下りるまでの間に営業することは、無許可での営業となりますので十分にご注意ください。
【4】さらに1~2週間後、許可が下りた場合は許可証の交付連絡があります。
この連絡を受けたら印鑑(認印可)を持参の上、警察署生活安全課の窓口にて受け取り、店舗内に掲示しましょう。
振動や騒音対策をする

壁や天井に吸音材・遮音材(パネル・パット・シート等)を取り付けるのはもちろん効果的ですが、それ以外にもコストを抑えて簡単にできる対策があります。近隣への迷惑がかからないよう、複数の対策を重ねることで振動や騒音を最小限に抑えていきましょう。こちらではいくつか対策方法を挙げておきますので参考にしてみて下さい。
・音楽・マイクの音量は大きくなり過ぎないよう上限を決め、調整は従業員が行う
・深夜のカラオケ・音響の使用を極力控える
・スピーカーは窓から遠ざけ、壁面に触れる部分や振動が伝わりやすいところに防振ゴムを入れる
・窓を防音サッシ・二重サッシにする
・出入口を二重構造にすることで、入退店時の音漏れを抑える
・お店の排気口や換気扇を防音タイプのものにする(吸音材を内張りしたダクトを取り付ける)
・扉や引き戸の内側に「お静かにお願いします」と張り紙をする
カラオケ導入にかかる費用相場
前述の通り、カラオケを導入するにあたっては、機材を揃えるのにかかる費用だけでなく、その後の維持費(ランニングコスト)もかかります。ここでは必要となる機材と費用相場についてみていきたいと思います。
必要なカラオケ機材一覧

カラオケ機材にかかる費用相場
カラオケ機材には、カラオケ本体のほか、マイク、スピーカー、液晶モニター等の周辺機器があり、インターネット回線を整えることも必要となります。それらは新品で購入するほか、中古品の購入、レンタル、リースといった選択肢があります。
新品を購入する場合の費用相場は、約100~300万円、中古品を購入する場合の費用相場は10万円前後となっています。
ただし、上記の費用相場はカラオケ機器単体の購入となり、周辺機器等は別途費用がかかるのでご注意ください。
また、カラオケ機材を導入する手段としてはレンタルやリースで一定期間借りることもできます。こちらはカラオケ本体に周辺機材を合わせた一式で月額3~5万円程度(※楽曲配信料は別途発生)となっており、大幅に初期費用を抑えることが可能。購入する場合には何年もかけて減価償却するのが一般的なので買い替えが難しいですが、レンタルやリースであれば契約期間ごとに新しい機器へ交換することができるのもメリットとなります。
ランニングコストの費用相場

ランニングコストとは一般的に、設備や建物を稼働・維持するために定期的にかかる費用のことを指します。
カラオケを導入する際にも月々のランニングコストはかかります。
カラオケのランニングコストとして、一つは、楽曲配信料。もう一つは、著作権料です。
楽曲配信料
楽曲配信料とは、楽曲の配信を受けたりカラオケ機器で再生したりするための費用です。通信カラオケに内蔵された全ての楽曲所有権は各メーカーのものとなっているので、その情報利用料として楽曲配信料を支払う必要があるのです。
機種によって料金は異なりますが、費用目安として月額10,000~17,000円程度です。なお、契約をしない場合または解約した場合には、20日程でカラオケ本体のロックがかかり、全ての機能が停止して使えなくなりますのでご注意ください。
著作権料
飲食店やスナックでカラオケを利用する場合には、著作権の手続きが必要になります。
音楽作品はもともとCD、放送、配信、演奏等どのように利用するかによって著作権の手続きが異なり、通信カラオケのメーカーとカラオケ利用店ではそれぞれが異なる利用手続きを行っています。
従って、飲食店でカラオケを利用する場合にも、日本音楽著作権協会のJASRACに対して音楽の再生・歌唱・上映に関する著作権の契約手続きを行う必要があり、著作権料として月額3,500円~16,000円の支払いが発生します。(※利用店舗の業態・規模・定員によっても金額が異なる)なお、手続きの申込みは、JASRACのサイトから調べて申し込むことも可能ですが、通常はカラオケ機器の代理店が窓口になってくれるのでそちらを経由して契約することをおすすめします。
・クラブ・スナックのおすすめ「店舗物件・居抜き物件」はこちら⇒
・カラオケ使用可のおすすめ「店舗物件・居抜き物件」はこちら⇒
その他、気になる業態から人気の居抜き物件をチェック
ラーメン店|居酒屋|イタリアン・フレンチ|和食店|中華料理店|
韓国料理店|焼肉店|うどん・そば屋|カフェ|カレー屋|
多国籍料理店|BAR|デリバリー|クラブ・スナック|ダイニングバー|
エステ|洋食・レストラン|美容室|物販|鉄板焼き屋|お好み焼き屋|
テイクアウト|焼鳥屋|イタリアン|フレンチ|
- 注目のキーワード
- おすすめの記事







