特集
【飲食店の税金対策】内装工事費にも適用できる「減価償却」とは? | 飲食店舗・開業ノウハウ
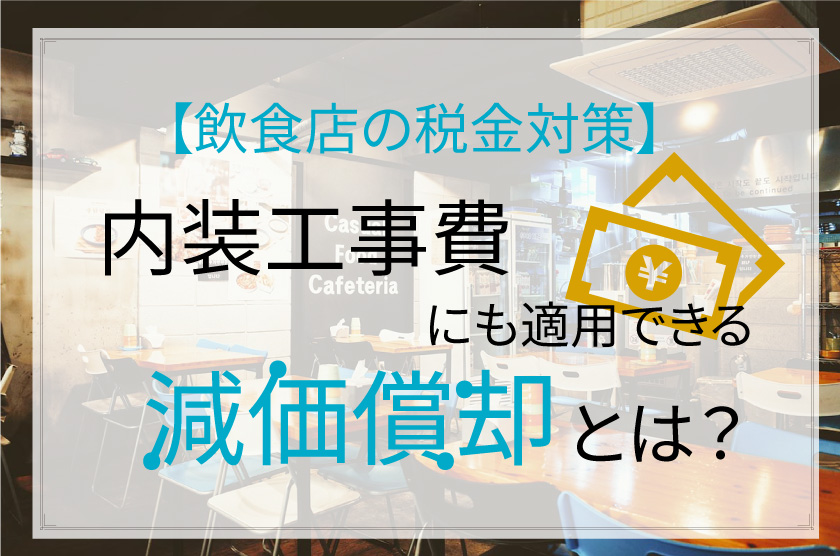
- 目次
「減価償却」は、開業者にとって非常に重要度の高い経理上の手法です。
お店をオープンした初年度は売上収入が小さい一方で、必要経費が大きく膨らみ赤字になってしまうことも少なくありません。そうした中でも、減価償却の処理をしっかりと行い、経費を数年間に分配計上することで、税金を抑えることが可能になります。
特に、厨房機器や内装工事費など高額な資産全般に減価償却を適用することができるため、初期投資が大きい飲食店開業を検討している方には是非頭に入れておいていただきたい考え方です。今回は、そうした減価償却の対象となる項目の中でも、内装工事費用の減価償却に焦点を絞って基本的な情報を詳しくご紹介していきます。
「減価償却」とは?
本題に入る前に、まずは「減価償却」とは何かについて簡単にご説明しておきます。
ほとんどの有形固定資産は、減価償却資産にあたります。
有形固定資産は、年月が経つにつれ劣化したり性能が落ちたりとその価値が下がってしまいます。そこで、その固定資産を毎年一定の割合で分割して費用計上する「減価償却」という考え方が用いられるようになりました。
もう少しわかりやすくするために、具体例を挙げて考えてみましょう。
例えば、60万円で製氷機を購入したとします。もちろんこの全額を経費として計上する必要はありますが、購入した年の経費に一括で計上してしまうのは誤りです。
なぜならば、その製氷機は購入した年だけでなく、その後何年も使用するものだからです。もしも、初年度にすべてを計上してしまうと、初年度のみ経費が膨らみ売上としては黒字になるはずが赤字になったり、2年目以降は0円で製氷機を使用していることにもなったりと、毎年の利益を正確に測れなくなってしまいます。
そのため、大きな金額がかかる厨房機器や設備などには、使用年数を鑑みて、分割で経費計上をしていく「減価償却」という方法が取られているわけです。
減価償却資産の「耐用年数」とは?
そこで重要になってくるのが「耐用年数」です。
ちなみにこの耐用年数は、必ずしも実際にその機器の使用可能年数とイコールではありません。また、もちろんオーナーが自由に決められるわけでもありません。もしも減価償却の期間をオーナーが自由に決めていいことになると、節税が自由にできてしまうことになるからです。そのため、それぞれの資産の経済的価値は、公平性に基づき国税庁が一律に定めています。まずは、国税庁のWEBサイトなどで該当する資産の耐用年数を確認してみましょう。
ここでは上述の例にならって製氷機の耐用年数を確認してみます。国税庁ホームページ内の「器具・備品の耐用年数一覧」によると、「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」は「耐用年数6年」となっていることがわかります。減価償却の計算方法にはいくつか種類がありますが、一般的には「定額法」が用いられます。定額法によると、60万の製氷機を購入した場合、60万÷6年=10万円となり、毎年10万円ずつ6年間に渡って経費として計上するということがみえてきます。
ちなみに、定額法の他に定率法、生産高比例法などの計算方法があります。特に税務署へ届け出ることがなければ、最も損益計算が安定している定額法が採用されることになりますので、その他の計算方法を希望される場合は、所轄税務署へ届け出ることも忘れないでください。
減価償却の特例制度
減価償却の対象は、法人・個人、また設備の種類によって決まります。そして減価償却には一部特例もあることを先にお伝えしておきます。それは、「少額減価償却資産の特例」と「一括償却資産の特例」です。それぞれに当てはまる条件については、下記に明記しますので参考にしてみてください。
少額減価償却資産の特例
【内容】
30万未満の資産であれば一括で減価償却することができる
【条件】
➀青色申告であること
➁個人事業主の場合は常駐の従業員数が1,000人以下であること(中小企業の場合は常時使用する従業員数が500人以下)
➂個人事業主 もしくは 中小企業であること
一括償却資産の特例
【内容】
10万円以上、20万円未満の資産は、法定耐用年数に関わらず一括償却資産として3年で一括償却を行うか、通常の減価償却を行うかを選択することができる。
※10万未満の資産に関しては、「消耗品費」として計上することができるため、上記制度に関わらず一括で減価償却可能
【条件】
白色申告、青色申告双方が利用可能
減価償却の対象となる内装工事費用
前述の通り、減価償却は時間の経過とともにその価値が下がっていく資産全般に当てはまります。もちろん建物の構造や付帯設備も立派な有形固定資産の1つです。したがって、飲食店において最も高額な費用を要する内装工事費用も減価償却の対象となります。
減価償却に関する基本的な仕組みを理解したところで、さっそく今回の本題である「内装工事の減価償却」に話を進めたいと思います。
内装工事の減価償却については、国税庁のホームページ内「耐用年数(建物・建物附属設備)」を参考にすれば、どのような工事が対象となり、耐用年数が何年なのかがわかるようになっています。具体的に飲食店の内装工事で対象となる項目とその耐用年数をピックアップして記載しておきます。
| 建物の構造(飲食店用) | |
| 木造・合成樹脂のもの | 22年 |
| 木造モルタル造のもの | 19年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 34年 |
| 金属造のもの | |
| 4㎜を超えるもの | 31年 |
| 3㎜を超え、4㎜以下のもの | 25年 |
| 3㎜以下のもの | 19年 |
| 店舗の内外装 | |
| アーケード・日よけ設備 | |
| 主として金属製のもの | 15年 |
| その他のもの | 8年 |
| 店舗簡易装備 | 3年 |
| 電源設備 | |
| 蓄電池電源設備 | 6年 |
| その他のもの | 15年 |
| 店舗内装用の器具・備品 | |
| 給排水・衛生設備・ガス設備 | 15年 |
| テーブル・イス・キャビネット | |
| 主として金属のもの | 15年 |
| その他のもの | 8年 |
| 応接セット | |
| 接客業用のもの | 15年 |
| その他のもの | 8年 |
| ベッド | 8年 |
| 陳列棚・陳列ケース | |
| 冷蔵・冷蔵機付のもの | 6年 |
| その他のもの | 8年 |
| その他の家具 | |
| 接客業用のもの | 5年 |
| 主として金属のもの | 15年 |
| その他のもの | 8年 |
| 内装用の電気機器 | |
| ラジオ・テレビ・テープレコーダー・その他 | 5年 |
| 冷房・暖房用機器 | 6年 |
| 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 | 6年 |
| 氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) | 4年 |
| 事務機器・通信機器 | |
| 電子計算機 | |
| パソコン(サーバ用のものを除く) | 4年 |
| その他のもの | 5年 |
| コピー機・レジスター・タイムレコーダーなど | 5年 |
| その他の事務機器 | 5年 |
| ファクシミリ | 5年 |
| インターホン・放送用設備 | 5年 |
| 電話設備とその他の通信機器 | |
| デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 | 6年 |
| その他のもの | 10年 |
| 看板・広告器具 | |
| 看板・ネオンサイン・気球 | 3年 |
| マネキン人形・模型 | 2年 |
| その他のもの | |
| 金属製のもの | 10年 |
| その他のもの | 5年 |
同じ固定資産でも、家庭用・店舗用・飲食店用では年数が異なります。上記はすべて、飲食店の場合の年数を表記しています。ご自分の店舗で該当する項目をご確認の上、耐用年数に応じた減価償却をおこないましょう。
また、もしも内装工事費や設備購入費が合算されている場合は、耐用年数の長い方に合わせる、もしくは平均値をとるという方法がとられます。いずれにしても、どちらにするかルールを統一し、間違いないのないよう気を付けましょう。
減価償却するための内装費用の仕訳
減価償却にあたっては、各費用の処理方法を決める「仕訳」の作業が必要です。具体的には、「建物」「建物付属設備」のいずれかの勘定科目に仕訳していくことになります。内装工事の請求書・請求明細書の内容を確認し、各勘定の処理を確定しましょう。
建物付属設備
「建物付属設備」として区分できるのは、その名のとおり付帯設備に関するものです。具体的には、電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備、冷房、暖房、通風設備、ボイラー設備、昇降機設備、災害報知設備、避難設備などが建物付属設備に該当します。
建物
「建物」は、店舗を開業する建物自体に直接実施する工事です。木工工事・ガラス工事・防水工事などがこちらに該当します。実際に仕訳を行う際には、まず建物付属設備をピックアップし、残った項目を建物に分類する方法が簡単です。
国税庁ホームページでは、仕訳区分を一覧にした表が公開されています。実際に仕訳を行う際は、請求書とこちらの表を見比べてください。
建物は構造・用途によって耐用年数が決められています。また、工事一式の合計費用によって上述した「少額減価償却資産の特例」「一括償却」「減価償却」のどれを利用することになるのかが決まります。
賃貸物件の耐用年数と減価償却の期間について
「建物」に分類される内装工事は、工事を実施した建物の用途変更・価値増加として考えられます。そのため、減価償却は建物の耐用年数に応じて考えるのが自然です。
一方、多くの飲食店は建物のオーナーからテナントを借りて開業するため、建物のオーナーと内装工事のオーナーが同じではありません。資産の権利も違うことになります。また、多くの内装工事は建物の耐用年数よりももたないため、すべての内装工事に建物の耐用年数を適応するのは現実的ではありません。
国税庁は賃貸物件で実施した内装工事に関して、「合理的に見積もった対応年数を適応する」といった内容を明記しています。一般的には、10~15年の耐用年数が適応されるケースが多いようです。ただし、建物の賃借期間に定めがある場合については例外として、その賃借期間が耐用年数として適応されます。
まとめ
飲食店の運営において、経理に関する仕事は非常に重要です。開業時の費用の大部分を占める内装工事の減価償却方法は、経理上で粗利を得るためにとりわけ大切なポイントとなります。
減価償却の方法についてはインターネットの情報を参考に勉強することも可能ですが、赤字計上になってしまった場合、信用喪失により銀行の融資が受けられなくなってしまうリスクもあるので、内装工事の内容を決める段階で税理士に相談するなど専門家の力を借りることをおすすめします。
- 注目のキーワード
- おすすめの記事















